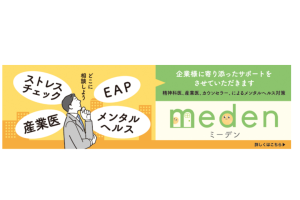目次
対人恐怖とは?かつて日本を代表する精神疾患
最近あまり耳にしなくなった「対人恐怖」という病気をご存じでしょうか。
この病名は1930年から1970年代にかけて広く使われ、日本の精神疾患を代表するほど多い病気とされていました。
「対人恐怖症」は「あがり症」とも呼ばれ、自分の容姿・におい・表情が他人を不快にさせてしまうのではないかと不安になり、強い緊張や回避行動につながるのが特徴です。
例えば、
-
人前で汗をかきすぎて恥ずかしい
-
腋の臭いで周囲に迷惑をかけている気がする
といった思い込みが強くなり、人前で極度に緊張して何もできなくなり、次第に人間関係を避けるようになります。
「恥の文化」と日本人の対人恐怖
日本人には「恥の文化」があると指摘されてきました。
これはアメリカの文化人類学者が述べたもので、日本人は他人の目を基準に自分を律し、恥をかかないことに強い意識を向けているという考え方です。
一方で、アメリカ人はキリスト教文化に基づき「神」という絶対的な道徳基準を持つため、日本人ほど他人の目を気にしないとされます。
この文化背景から、対人恐怖は「Taijin-Kyoufu-sho」として海外に紹介され、日本特有の病気と見なされていた時期もありました。

対人恐怖から社交不安症へ―病名の変化
しかし1980年、欧米でも同様の症状があることがわかり、**「社会恐怖(Social Phobia)」**という診断名が登場。
その結果、「対人恐怖」は「社会恐怖」に吸収され、使われなくなっていきました。
さらに国際的な診断基準の変更により、病名は以下のように変化しています。
-
1980年:「社会恐怖」
-
1994年:「社会不安障害」
-
2008年:「社交不安障害」
-
2013年:「社交不安症(Social Anxiety Disorder)」
ひとつの病気でこれほど病名が変化するのは珍しく、研究や社会の理解の進展を反映しています。
社交不安症の症状と発症のきっかけ
社交不安症とは、人前に出ることや注目を浴びることに強い不安を感じ、日常生活に支障が出る病気です。
日本では現在およそ100万人が患っていると推定されています。
発症は小中学生の頃が多く、
-
学校の発表で手が震えて笑われた
-
恥をかいた経験から、人前に出ると異常に緊張するようになった
といった体験がきっかけになります。
やがて一対一の会話でも緊張し、人との関係を避け、ひきこもりの原因になることもあります。
大人になると、不安を紛らわすためにお酒に頼り、アルコール依存症を併発するケースもあります。
HSPとの混同と誤解
近年「HSP(Highly Sensitive Person)」という言葉がメディアで広まりました。
HSPは相手の気持ちに敏感な性格傾向を指しますが、医学的な病名ではありません。
「自分はHSPかも」と精神科を受診する人の中に、実際には社交不安症が隠れているケースもあります。
社交不安症の原因と治療法
社交不安症は心理的な要因だけでなく、脳神経の働きの異常も関わっていると考えられています。
薬物療法
-
SSRI(例:レクサプロ)が有効
-
軽症なら抗不安薬も使用可能
放置すると仕事や学業に支障が出るだけでなく、ひきこもりや依存症につながるため、早期の受診が重要です。
カウンセリング(認知行動療法)
認知行動療法は、
-
緊張を振り払おうとして余計に緊張する
-
他人の目を気にしすぎ、自分の体の反応に注意が向きすぎる
といった認知のゆがみを修正し、不安を和らげます。薬と組み合わせることでさらに効果が高まります。
コロナ禍と社交不安症
コロナ禍でマスクやオンライン生活が広がり、社交不安症の人にとって過ごしやすい環境になったとも言われます。
今後オンライン化が進めば、社交不安症の人がより生きやすい社会になるかもしれません。
ただし、現在の生活に支障が出ている場合は、早めに医療機関へ相談することが大切です。