「産業医面談って本当に意味があるの?」
「実際に受けたけど、何もしてくれなかった気がする…」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。確かに産業医面談では治療や薬の処方は行われません。しかし、産業医面談は従業員の心身の健康を守り、職場環境を改善するために非常に重要な役割を担っています。
この記事では、特にメンタルヘルスに関わるケースを中心に、産業医面談の5つの役割をわかりやすく解説します。
目次
産業医面談が必要となるケース
産業医面談は、以下のような場面で実施されます。
それでは、実際に産業医面談でどんなサポートが受けられるのか、5つの役割を順番に見ていきましょう。
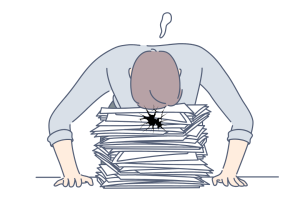
① 今の心身の状態をチェックしてくれる
ストレスチェックで高ストレス判定が出た場合、希望すれば産業医との面談が可能です。
産業医は、結果をもとに労働者と面談を行い、現在の心身の状態を確認します。これは早期発見・早期対応につながる大切な役割です。
② 働き方や生活習慣の改善アドバイス
長時間労働や生活習慣の乱れがメンタル不調につながることは少なくありません。産業医面談では、働き方の改善や生活習慣の見直しに関するアドバイスが受けられます。
場合によっては産業医から会社に対して「残業を減らすように」などの指導が入ることもあります。
主治医との大きな違いは、産業医は会社の実情を踏まえた現実的な働き方のアドバイスをしてくれる点です。
③ 精神科受診が必要かどうかを判断してくれる
高ストレスだからといって、必ずしもうつ病や適応障害とは限りません。
しかし、産業医面談で「精神科を受診した方が良い」と勧められる場合は、既に心の病気が発症している可能性があります。
産業医はその判断を行い、必要に応じて医療機関への受診を促してくれるのです。
④ 休職・復職の妥当性を確認してくれる
休職に入るときや復職を検討するときにも、産業医面談は重要です。
-
休職時:主治医の診断書を確認し、職場環境との関係をヒアリング
-
復職時:主治医の復職可診断があっても、本当に働ける状態かを再確認
たとえば職場が繁忙期であれば、復職を少し延期した方が良いと産業医が判断する場合もあります。労働者を守る視点から、復職のタイミングを調整する役割を担っています。
⑤ 職場環境の改善を会社に指導
メンタル不調の原因が職場環境にある場合、産業医は労働者の同意を得て会社に改善を指導します。
実は、平成8年の労働安全衛生法改正により、産業医には会社に対して助言・指導を行う権限が認められています。
つまり、産業医面談をきっかけに職場環境が改善される可能性があるのです。
「産業医面談は意味ない」と言われる理由
一部の人が「産業医面談は意味がなかった」と感じるのは、産業医が治療をしてくれる医者ではないからです。
産業医は診断や薬の処方といった医療行為を行うことはできません。そのため「何もしてくれなかった」と誤解されがちです。
しかし、治療を行わないからこそ、中立的な立場で労働者の健康と職場環境の両方を考慮した判断をしてくれるのです。
まとめ:産業医面談を上手に活用しよう
産業医面談は「意味ない」のではなく、
-
体調チェック
-
働き方や生活習慣のアドバイス
-
精神科受診の判断
-
休職・復職のサポート
-
職場環境改善の提言
といった5つの大切な役割を持っています。
治療はできなくても、産業医はあなたの健康と働きやすさを守るパートナーです。
「相談しても無駄」と思わず、ぜひ産業医面談を積極的に活用してみてください。
