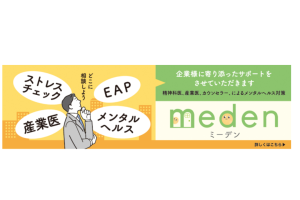日本では企業のハラスメント行為、メンタルヘルス問題が年々社会問題として取り上げられてきています。そして、社内でのハラスメント行為やメンタルヘルス不調を相談し、改善につなげるために重要な機関が相談窓口です。
相談窓口には社内相談窓口と社外相談窓口の2種類があります。今回は、社内相談窓口、社外相談窓口の違い、そして、それぞれのメリットとデメリットを解説していきます。
目次
【相談窓口とは】
まず、職場における相談窓口とは、従業員がハラスメント行為やメンタル不調、人間関係、職場環境などの悩みに対応する機関です。
悩みの相談を受けるだけでなく、その後の問題解決や職場改善指導なども行います。
人事評価に影響しないよう、独立した機関である必要があり、人事や経営者が相談員として担当することは望ましいとされていません。
相談窓口の有無は従業員のメンタルヘルスケアに加え、エンゲージメントにも影響を与えています。企業として「ハラスメント行為を許さない」、「従業員のことを考えている」という意思表示になり、従業員からの信頼につながりやすいからです。
2020年パワハラ防止法が施行されました。
日本ではすべての企業でパワハラ防止策が義務化され、その中で、相談窓口を設置することが義務付けられています。法律で義務化されただけでなく、社会的にもハラスメント行為には厳しい目が向けられ、企業にとって重要課題の1つになっています。また、労働安全衛生法第69条では、事業者は従業員が健康に働ける環境を整備し、メンタルヘルスの維持・改善に努めることも義務付けられています。つまり、ハラスメント問題、メンタルヘルス問題、どちらも企業がしっかりと対策をとるようにと義務付けがされているのです。
次に、社内相談窓口と社外相談窓口の違いについて説明しましょう。
企業の設置する相談窓口には、社内相談窓口と社外相談窓口の2種類があります。基本的には、社内相談窓口、社外相談窓口どちらも設置することが望ましいとされています。
【社内相談窓口と社外相談窓口(外部相談窓口)の違い】
【社内相談窓口】
社内相談窓口は自社でカウンセラーなどを雇用して設置する専用の相談窓口です。社内に窓口が置かれることから、従業員がすぐに相談しやすく、早急な対応がしやすいという特徴があります。仮に相談員を雇用したりせず、専門家ではない、社内の従業員に任せる場合、人事評価に関わらない社員を選任するようにします。選任する従業員は、メンタルヘルスに対する最低限の知識を持っておく必要があります。
社内相談窓口は、社内に相談員が常駐していることから、何か問題があった際もすぐに人事などと連携がとりやすいのも良い点と言えます。社内に設置する場合は、個人の秘密が漏えいしないように対策することと、相談したことが周囲にわからないように配慮することが重要です。

【社外相談窓口】
社外相談窓口は名前の通り、社内に相談窓口を設置するのではなく、外部に依頼して相談窓口を設置することを言います。オフィス内に窓口を設置できない、または専門の人材確保が難しい場合におすすめです。
社外相談窓口はメンタルヘルス・ハラスメントの専門家がチームで対応することから、手厚い対応、医療機関との提携など、安心して企業側は任せることができます。また、個人情報が漏えいするリスクが低く、企業との癒着関係が発生しにくいという特徴があります。
また、専門家による具体的なハラスメント防止策やメンタルヘルス不調者への対応など職場改善の提案も期待でき、第三者の視点から対策できる点も優れています。中小企業が適切な社内相談窓口を設置するのはコスト面でも負担になりやすいため、社外相談窓口のほうが適しているケースも多いです。
社内相談窓口と社外相談窓口には、それぞれ違った特徴があり、それぞれのデメリットをカバーできるため、どちらも設置することが推奨されています。しかし、専用の部屋を用意する必要やカウンセラーを雇用したりなど、社内できちんと機能する相談窓口を設置しようとすると費用がかかります。そのため、中小企業は外部機関に委託することがおすすめです。
次に社内相談窓口と社外相談窓口のメリットとデメリットについて解説していきます。
【社内相談窓口のメリット】
次に紹介するものが社内相談窓口のメリットと言えます。
l 相談員が会社側と連携を取りやすい
l 社内状況を理解しているため、相談員が相談者の悩みを理解しやすい
l 社内の状況を調査しやすい
l 従業員はいつでも相談できる
l 社内での啓発活動が実施しやすい
l 専属産業医、産業保健スタッフと連携が取りやすい
相談員を自社雇用していることから、産業医とともに衛生委員会などに参加することもメリットと言えます。
相談員は社内状況をよく理解しており、相談者の悩みを理解しやすい点もメリットです。
相談員の立場からしても、社内でのハラスメント対策と研修による啓発活動がしやすく、メンタルヘルス不調の早期発見・対応が可能になります。
【社内相談窓口のデメリット】
社内相談窓口にはいくつかのデメリットもあります。特に公平性や相談者・相談員の双方の心理的負担から次のデメリットが考えられます。
l 立場上、公平性が保ちにくい
l 環境をきちんと整備しないと、相談しづらい環境になる
l 情報漏洩の可能性がある
l 費用面で負担が多い
l チームでの対応が難しくなる。
I専門的対応がしづらい
社内相談窓口を設置する場合、隔離された部屋や従業員が相談していることを周りに分かりづらい体制づくりが必要です。また、専門家でない従業員を相談員にすると、誤った対応をとってしまい大きな問題につながってしまうことや、そもそも相談窓口として機能を果たしていないというケースが多く見受けられます。しかし、専門家の相談員を別で雇用すると大きな費用がかかってしまう点もデメリットです。
次に社外相談窓口のメリット・デメリットについて解説していきます。
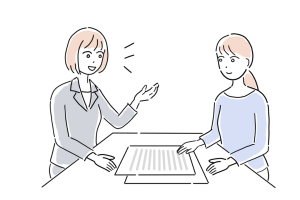
【社外相談窓口のメリット】
社外相談窓口は、次のようなメリットがあります。
l 会社に相談したことを知られる心配がない
l 従業員が相談しやすい
l 費用負担が少ない
l 専門スタッフがチームで対応するため、対応が手厚い
l 専門的な立場から職場改善指導をもらえる
l 専門の相談員が相談を行う
l 企業の人事・労務担当者の負担が少ない
l 具体的かつ的確な予防策が期待できる
社外相談窓口を置く最大のメリットは、従業員の相談内容や相談した人の個人情報が企業側に漏れる心配がほとんどない点です。従業員が安心してメンタル不調やハラスメントの悩みを相談しやすいのが何よりの利点です。
また、社内で相談窓口を設置するよりも、外部機関に依頼する方が費用が少なくて済みます。
社内で相談員を雇用せず、専門家がチームで対応してくれることから、中小企業では、外部委託することがおすすめです。
相談窓口の設置は法律で定められた義務であり、専門家である社外相談窓口の存在は企業イメージの向上、コンプライアンス意識の改善にもつながります。
【社外相談窓口のデメリット】
社外相談窓口には次のデメリットがあります。
l 会社に知られることなく相談できる分、問題が見えづらくなる
l 社内状況が見えないため、職場状況をリアルタイムで追いづらい
企業側に知られることなく相談できるため、企業側に問題が見えづらい点があります。また、個人が望まなければ、企業側に相談内容を開示することはないため、事業主は社外相談窓口に対して、意義を感じられなくなってしまう可能性もあります。
従業員のプライバシーを保護する観点から、これは仕方のないことと言えますが、ハラスメント・メンタルヘルス対策はとても数値化することが難しい事と重なり、余計な経費と判断されてしまうこともあります。
以上、社内相談窓口・社外相談窓口の違いとメリット、デメリットについて解説しました。
メンタルヘルスで最先端をいくアメリカでは、メンタルヘルス対策・相談窓口を外部に委託するEAP機関を導入している企業は9割と言われています。そのため、今後日本でもメンタルヘルス対策や相談窓口を外部に委託する企業が多くなっていくでしょう。
企業としてのコンプライアンス意識も問われる重要な課題ですから、相談窓口の設置は早急に行うべきです。ハラスメントやメンタルヘルスの問題を改善し、働きやすい職場づくりを進めましょう。