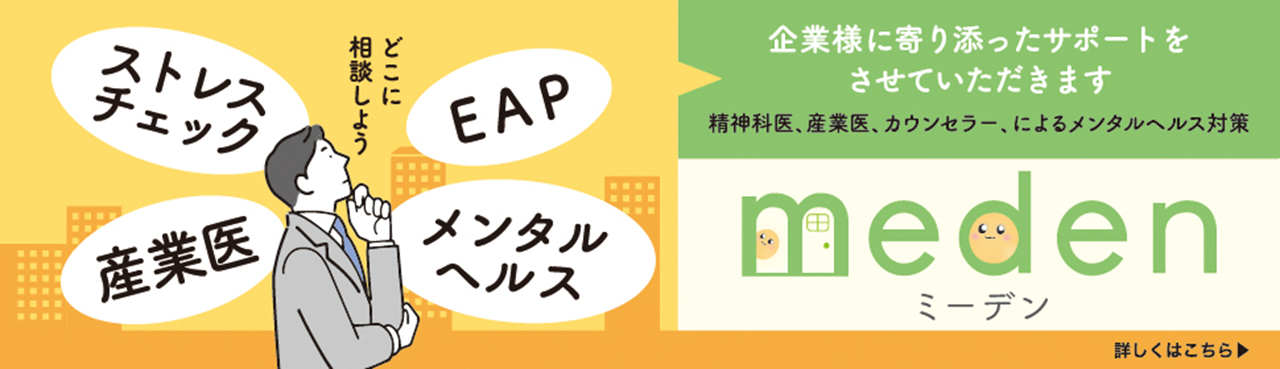従業員が休職した時にすべきこと
更新日:2025年3月11日
会社にとって、従業員の休職は避けられない問題のひとつです。特にメンタルヘルス不調などによる長期休職は、本人だけでなく職場の生産性やチームの士気にも影響を与えます。適切な対応を行うことで、休職者がスムーズに復帰できるだけでなく、他の従業員の安心感を高めることにもつながります。
そこで今回は、従業員が休職に入る前から休職後、そして復職するまでの対応で会社側としてすべきことを流れに沿って、解説していきます。
1.休職制度とフローの明確化
休職が必要になった従業員が、どのような手続きを踏めばよいのかを明確にすることが重要です。会社の規定によって、「どの程度の期間休めるのか」「どのような条件で休職できるのか」 などが異なります。従業員にとってわかりやすい形で、社内ルールを整理しておきましょう。
例えば、次のような情報を明文化しておくとスムーズです。
- 休職の対象となる条件(病気・ケガ・メンタル不調など)
- 申請に必要な書類(診断書の有無など)
- 休職期間の上限と延長の可否
- 休職中の給与や社会保険料の取り扱い
- 復職の判断基準
従業員が混乱せずに申請できるよう、就業規則や社内ポータルサイトで情報を共有しておくことが大切です。
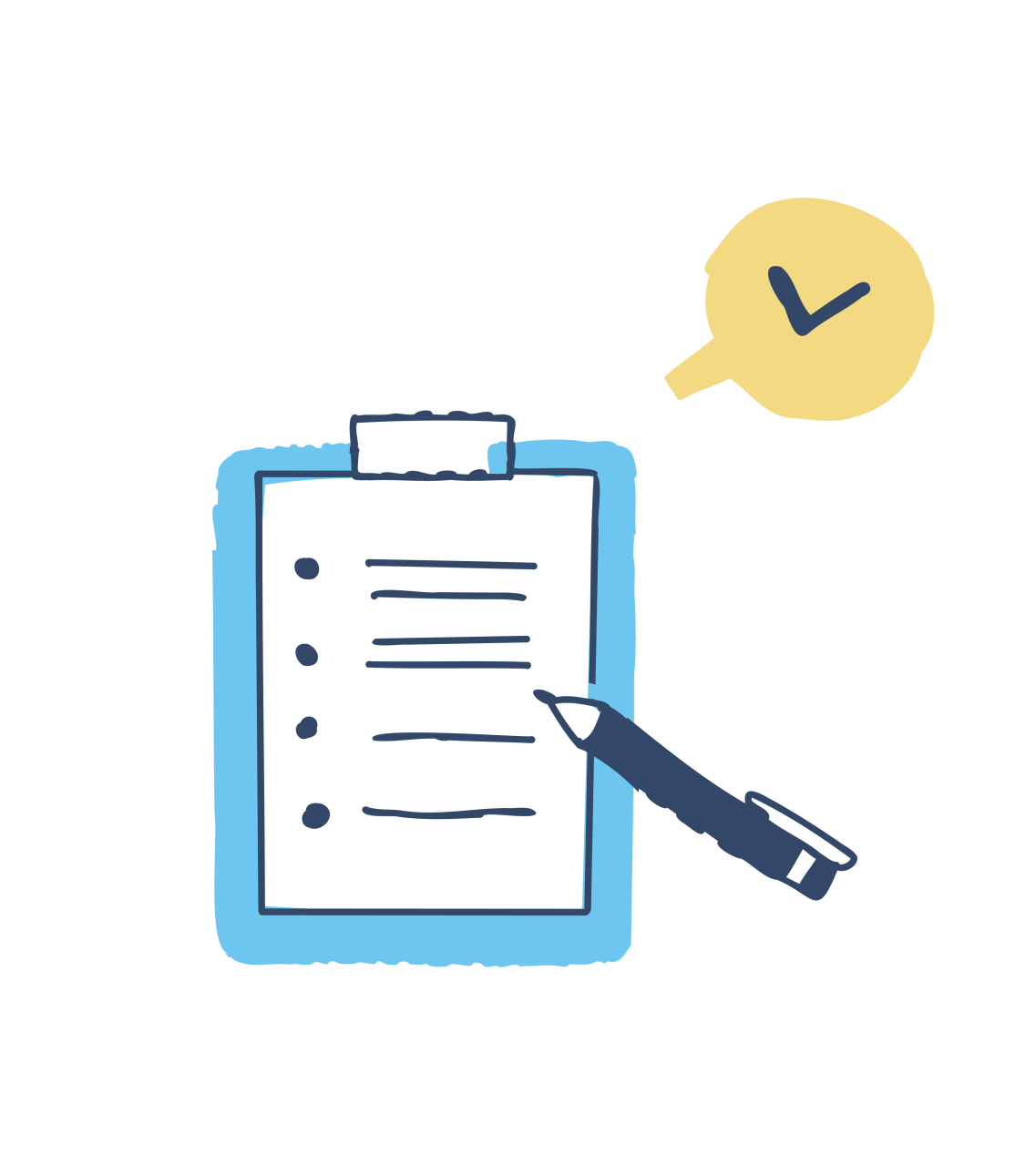
2.本人の健康状態の把握と適切なフォロー
休職が必要な従業員の健康状態を正しく把握し、無理のない形で休職に入れるよう配慮することも重要です。
休職を決める際には、次のような点を確認しましょう。
- 医師の診断結果と意見
- 本人の意向(どの程度の期間休みたいのか)
- 仕事の負担や職場環境の問題

3.チームや関係者への周知と業務の引き継ぎ
休職する従業員の業務が属人化していると、休職後に他のメンバーの負担が急増してしまいます。そのため、可能な限り休職前に業務の引き継ぎを行うことが望ましいです。
- 休職者の業務をリスト化し、 誰がどの業務を引き継ぐのか決める
- 必要に応じて、 マニュアルや引き継ぎ資料を作成する
- チームメンバーに対し、 休職の経緯や業務の分担について説明する
ここで大切なのは、 休職者のプライバシーに配慮しながら情報を共有すること です。「〇〇さんが体調不良でしばらくお休みすることになった」など、 過度な情報開示は避けつつ、チームが混乱しないよう伝えましょう。

4.休職期間中の対応
実際に休職が開始したら、本人との連絡は1~2ヶ月に1回の面談もしくはメールでの体調確認だけにして、頻繁に連絡することは避けてください。休職期間中は、できるだけ仕事や、職場の人と離してあげることが大切となります。会社側からの頻繁な連絡は、本人の負担となり、具合を悪化させる可能性があります。また、心配だからと言って、本人の許可なしに家族に連絡することも避けましょう。

5.職場改善
従業員が休職してしまった場合、何が問題だったのか、状態が落ち着いたのを確認してから、話し合いの場を設けるようにしてください。会社責任である場合は、二度と同じようなことが起こらないように職場改善を実施する必要があります。従業員が復職してきても、職場が改善されていなかった場合、また同じことの繰り返しになります。何がいけなかったのか、しっかり話し合うことで、再発防止だけでなく、第二、第三の休職者を出すことを防ぐことができます。
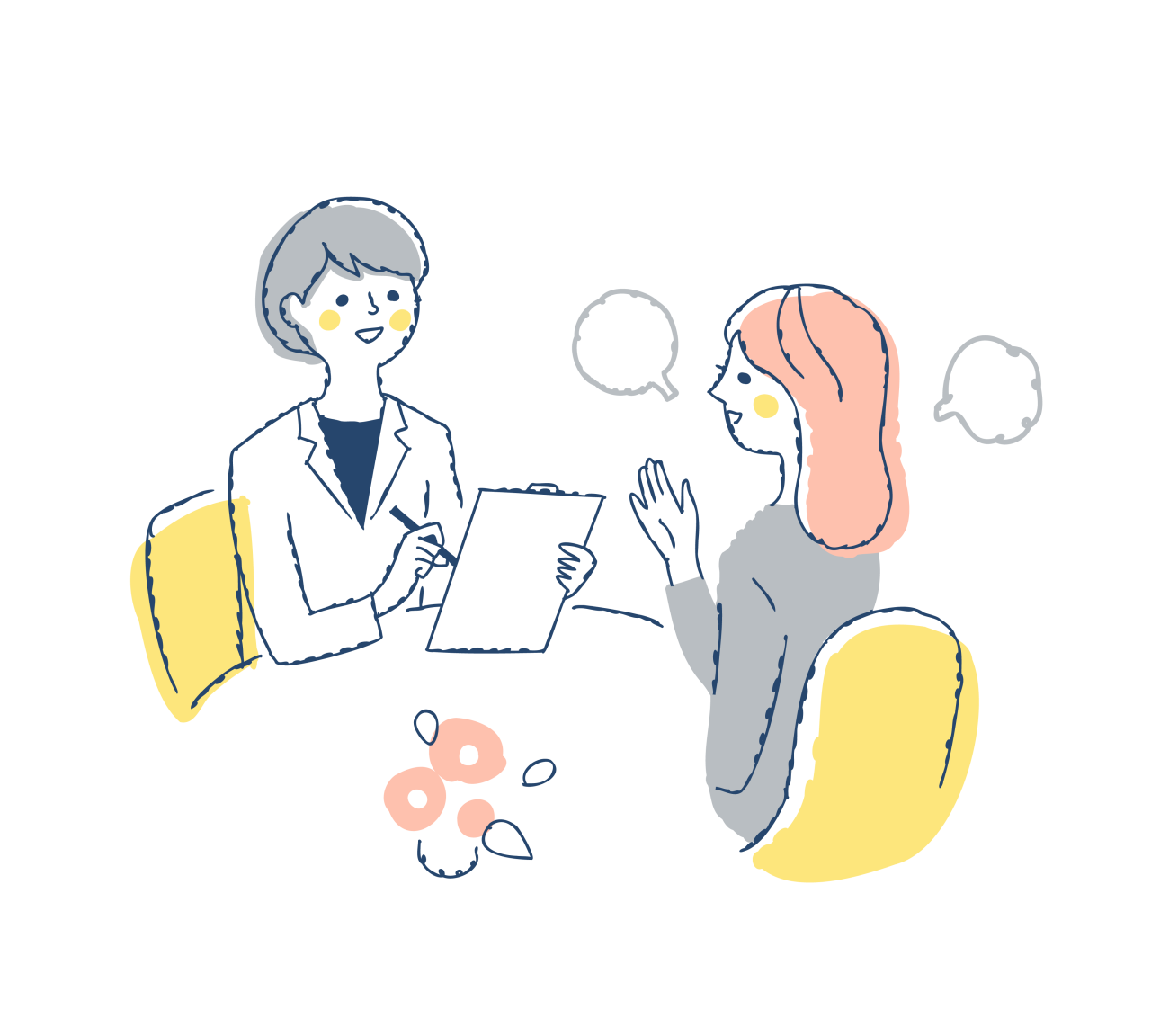
6.復職したときのサポート体制の整備
復職してきても、今まで通り働けるようになるまで時間がかかります。どのようにサポートしていくのか復職プログラムの形で決めておくことは大切です。復職プログラムをあらかじめ決めておくことで、混乱を防ぐことができます。
7.復職が決定したら
復職の目処が立ったら、事前にリハビリ勤務の可能性を相談します。復職前にリハビリをするかしないかでは再発率が変わってきますので、必ず出勤練習を行うようにします。
また、正式な復職が決定したら、今後どのように働いていくか本人と話し合いの場を設けます。産業医がいる場合は産業医の意見を聞き、いない場合は主治医の意見書を参考に、今後の働き方について話し合いましょう。あらかじめ職場で決めておいた選択肢の中から、部署異動させるか、元の部署に戻るか、担当上司を変えるかなど、ある程度本人の意向をくみ取るようにしてあげると良いでしょう。

今回は、従業員の休職~復職までの流れで、会社側としてすべきことを解説しました。
休職は決してネガティブなものではなく、適切な対応をすれば 「健康的に働ける職場環境の整備」 につながります。従業員が安心して休み、無理なく復帰できる仕組みを整えていきましょう。
また、何か休職者の対応でお困りの際はミーデンへご相談ください。