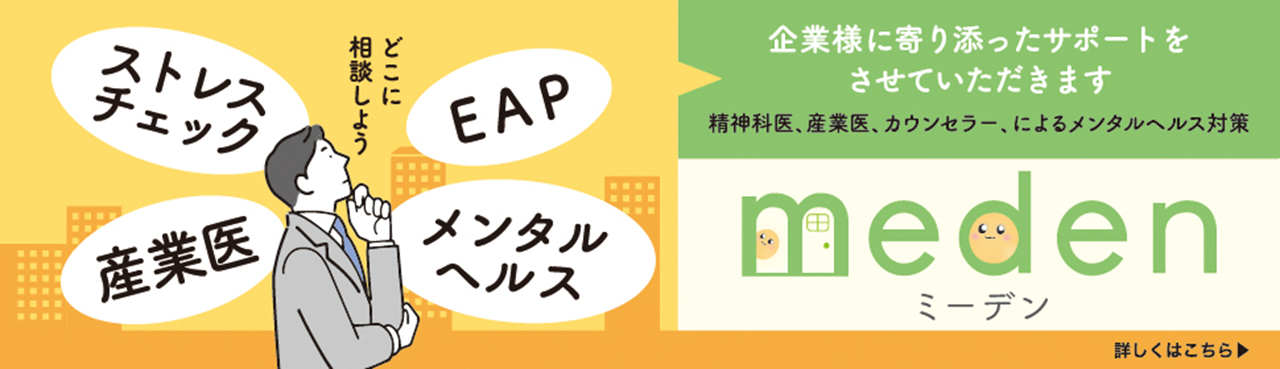適応障害療養中にやってはいけないこと
更新日:2025年5月12日
適応障害とは、日常生活の上でのストレスが原因で、心や体に不調が出ている状態です。最近では「障害」という名称が差別的であるので、「適応反応症」とも呼ばれています。
症状としては、うつ、不安や緊張、イライラなどがあり、軽いうつ病と考えたら良い状態です。働き過ぎ、我慢しなければならない人間関係が続くなど、原因となった日常的なストレスとの因果関係が明らかであり、そのストレスから1ヶ月以内に発症することが診断の条件です。
日本の働いている人の休職の理由で1番多いのがうつ病で、2番目が適応障害です。それくらい適応障害は多い病気なのです。
適応障害とうつ病の違いは、原因が明らかであることと症状が軽いことです。原因が明らかでも症状が重ければうつ病と診断されます。ですからうつ病と適応障害には境界線がありません。うつ病の症状は仕事を休んだとしても半年から1年半くらい続きますが、適応障害ではストレスがなくなると半年以内には症状が改善します。
適応障害を放置すると、症状が重くなりうつ病になってしまいます。それだけ治療にも時間がかかってしまうでしょう。そこで、今回は適応障害と診断されてから、やってはいけないことを紹介しましょう。

1.ストレスを放置する
治療を受けたとしても、ストレスを放置したまま過ごしてしまえば病状は改善しません。原因が明確であることが適応障害ですが、実際に原因が1つということはなく、いくつかのストレスが絡んでいることが多いようです。例えば、医師には過労が原因だと伝えても、それだけでなく同時に上司とうまくいっていなかったり、家庭がうまくいっていなかったり、というケースもあります。一度に全部を解決することはできませんが、1つずつ解決することが必要でしょう。特に職場の問題は、産業医や人事担当者とよく相談して働く環境を改善してもらうべきです。1回言ったきりでは深刻さが伝わらないこともあるので、きちんと改善するまで言い続けることが大切です。
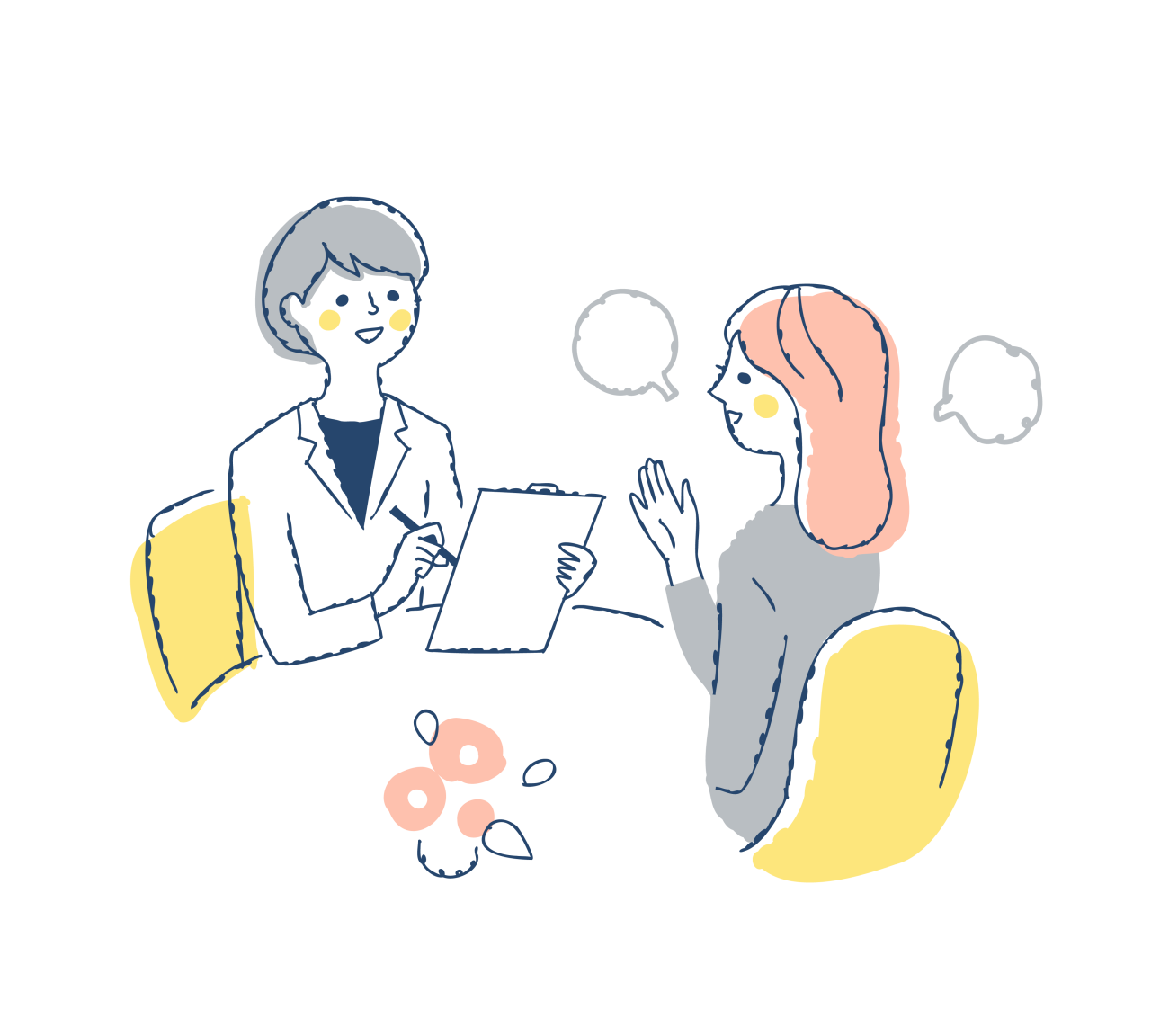
2.休みをとらない
適応障害の治療の基本は、原因であるストレスを避けて、ゆっくり休むことです。治療を受けても休まなければ治りません。1カ月以上の休職をして、自宅で心と体を休めましょう。ゴロゴロするのも良いですが、できる範囲で自分が楽しめることやストレス解消になることをするのもおすすめです。

3.夜更かし、飲酒
休職をとったからと言っても、毎晩ゲームや動画で夜更かしをしていては回復につながりません。何よりも夜の睡眠時間を大切にして、規則正しい生活を心がけましょう。食事の時間も決めるようにして、朝食もきちんと摂るようにしましょう。
また部屋にこもりっきりの生活も良くありません。散歩でも構わないので体を動かすことも回復につながります。
アルコール類は回復を妨げることがあるので、毎日の飲酒は好ましくありません。

4.療養中に何か始めようとする
療養の目的は、ストレスの原因から離れることを通して、弱った心と体を蘇らせることが目的です。ところが1~2カ月の休職がとれると、「この療養期間を利用してスキルアップを目指そう」と考える人もいます。集中力が落ちているので何か習い事をしても身につきません。それどころか、回復を遅らせる引き金にもなってしまいますので、新しいことを始めることは避けましょう。
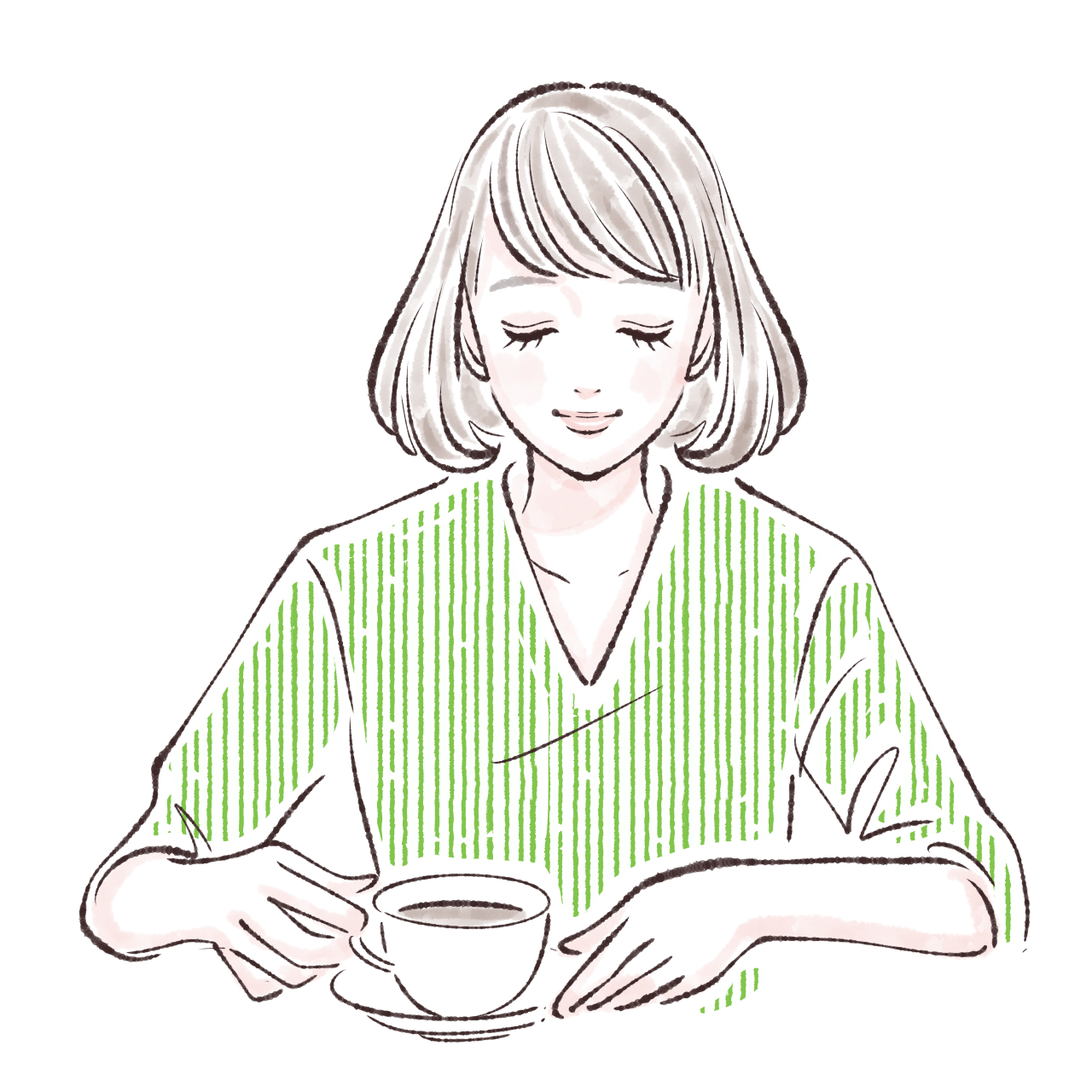
5.働き方を変えない
無事回復して復職しても、また同じ場所で同じ働き方をしてしまったら症状をぶり返すだけです。復職前に何のために働くのかを考えることも必要でしょう。
人が働く目的には3つあります。お金のため、生きがいのため、そして世の中に貢献するための3つです。いくら給料が良いからといっても、地獄のような職場で働き続けていたらいつか心は病んでしまいます。生きがいの仕事といっても、お金を稼げなければ家族に迷惑をかけてしまいます。3つのバランスをよく考えて、不満のない職場で働くことが大切です。これが期待できないならば、転職も視野にいれなくてはいけません。

適応障害になるストレスは、人によって異なります。ある人にとっては居心地の良い職場であっても、ある人にとっては過度なストレスがかかる会社にもなりうるのです。仕事量の問題、ポジションの問題、人間関係の問題など、その立場になってみないと分からないことがたくさんあります。適応障害になってしまうのは、心の弱さが原因ではなく、その人の性格と環境の歯車が合わないことが原因なのです。
例えば、人付き合いが苦手な人が営業の仕事につく、ジッとしているのが苦手な人が経理の仕事をするのでは心を病んでいくのは当然でしょう。そんな時に、「自分の問題だ」、「自分が変わらなくては」と考えるのでなく、「ここは自分に合っていない」と考えるべきです。