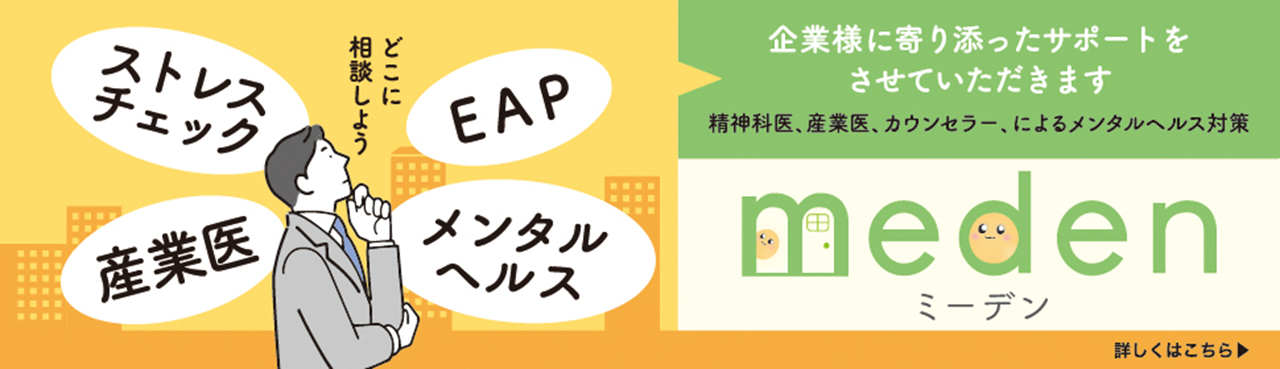産業医と臨床医の違い
更新日:2025年4月8日
産業医面談を受けた人の中で、「あれ?治療してくれないの?」「薬をくれないの?」そんな思いをしたことがある人も多いかと思います。そうすると、産業医は意味がない、何のためにいるのか、と怒りの声すら出てきます。このような声が出てきてしまう一つの要因は、産業医という職務が間違った解釈をされているということが考えられるでしょう。
そこで、今回は産業医と臨床医の違いについて解説していきます。産業医と臨床医の違いを理解することで、産業医に対する理解が深まると思います。ちなみに、臨床医とは普段みなさんが通われている病院で診察してくれる医師のことを指します。それでは、いきましょう。
まず、産業医は、内科や精神科など他の診療科と兼任して産業医活動を行っていることが一般的です。普段は開業医として働いていたり、病院に勤めていたり、基本的には臨床医です。産業医としての活動は、1~2ヶ月に1回の職場巡視や産業医面談、健康診断の結果のチェック、衛生委員会の参加など、会社側から要望があった時に行います。
産業医と聞くと、内科、外科、精神科などと同じように産業科という専門科があるのではないかと思いますが、産業科というものはなく、産業医は、内科、外科、精神科などの専門科をもちながら兼任して産業医活動を行っているのです。ですので、産業医という専門医がいる訳ではなく、産業医資格を持った医師が会社で産業医活動を行う時に産業医という呼ばれ方をすると考えた方が分かりやすいかも知れません。ちなみに産業医資格は医師であれば、講習を受けることで取得することができます。細かいですが、会社は産業医と契約をするという言い方ではなく、医師を産業医として選任するという言い方をします。
ただ、産業医と臨床医の仕事は全く異なります。産業医の仕事は、従業員が健康的に働けるように指導したり、職場状況をチェックしたりします。具体的には、健康診断の確認、休職・復職面談、職場巡視、衛生委員会の出席、会社への職場改善指導などです。一方で、みなさんもご存じのように、臨床医は診察、検査、診断、薬の処方、手術などを行います。
ここで重要なことは、産業医は医療行為をしないということです。というより、産業医としての活動は医療行為ではないと考えると分かりやすいでしょう。そのため、従業員を診断し、病名を付けたり、薬を処方したりすることができないのです。
よく「産業医に見てもらったのに薬をくれなかった」、「ただ病院に行けと言われた」という意見を耳にすると思いますが、これは産業医は医療行為ができないという理由があるためです。
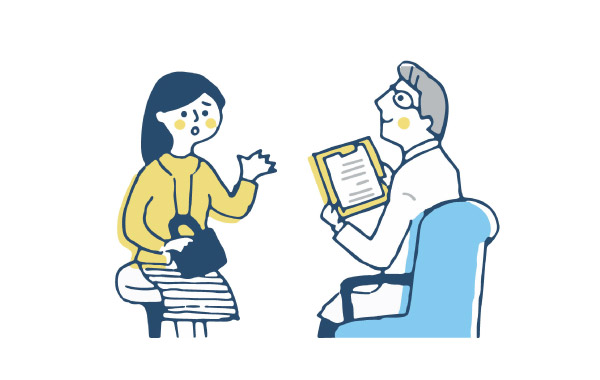
次に立場としての話をします。まず、臨床医は患者の味方です。患者が円滑な日常生活を送れるよう診察、治療を行います。しかし、産業医は従業員と会社どちらもの味方であり、中立的な立場をとります。産業医は職場全体の健康と安全を確保し、従業員の健康を維持するために中立的な立場にいないといけないのです。ただし、報酬は会社側から貰うため、従業員としては、産業医は会社側の味方をしていると思いがちです。しかし、そもそも会社と従業員は敵対同士ではありません。ですので、考え方としては、会社と従業員との間を持つ調整役や、仲介役と考えると分かりやすいかと思います。例えば、臨床医がうつ病を患っていた従業員に対して復職可能と判断した場合でも、産業医は職場状況を考えながら最終的な復職判断をします。職場が繁忙期で復職する従業員を受け入れる体制が整っていなかったり、休職前の職場状況に改善が見られていない場合は、復職を遅らせるケースもあります。これは職場側が混乱しない目的でもあり、従業員側のうつ病の再発を防ぐためでもあります。その他のケースとしては、会社側が従業員を過重労働させていた場合、産業医から会社側に指導するというケースあります。これらの役割は、臨床医にはできません。ですので、産業医は臨床医と違った大切な役割を担っているのです。

以上、産業医と臨床医の違いについて解説しました。
確かに、医療行為のできない産業医に対して意味がないと考えてしまうのは仕方のないことかも知れません。しかし、産業医はあくまで会社と従業員との中立の立場でいなくてはならないため、患者の味方になる臨床医としての立場を取れないのです。
ただ、そうすることで産業医にしかできない役目を果たすことができるのも事実ですので、産業医に対して悪いイメージがなくなってくれることを願っています。